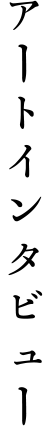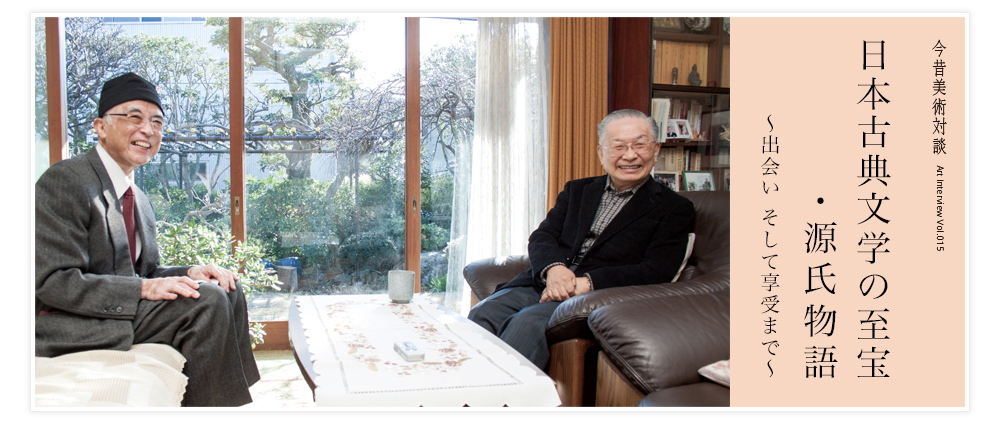そこから生み出される新しい時代の美術のかたち。幕末・明治の変革期に絵筆を持った画家たちの姿を追想する。
| 加島
前回は、幕末・明治の画家たちについてお話いただきました。特に今後の再評価に期待が大きい渡辺省亭について、面白いお話を伺いました。後編も引き続きよろしくお願いいたします。
野地
よろしくお願いいたします。
加島
まず、前回からの引き続きで、省亭の大々的な展覧会がなぜ日本でなかなか開催されないのか、という疑問についておうかがいしていいでしょうか?
野地
ひとつ、大きな理由は、いい作品が海外にあるということですね。
加島
日本には、たとえば大きな屏風みたいな作品っていうのはないんですか?
野地
一番有名なのは赤坂離宮の大食堂に七宝焼の額絵があるんですけど、その原画が省亭なんですよ。
加島
そうなんですか。
野地
面白いエピソードがありましてね。当時、赤坂離宮の内装をどうするかっていってコンペをするんですよ。で、荒木寛畝と渡辺省亭が最後に競り合うんですよね。そのコンペに出した原画が東博に残っていまして、それがまたすばらしい出来なんですよね。なんだかルイ王朝の壁画のようなね。神々しいばかりの写実力。あれを見ると、寛畝はもちろん上手い人なんだけど、どこかに江戸趣味みたいのが入っている。そこから切り離そうとした時代の、しかも西洋式の宮殿のなかにどっちがふさわしいか、と考えると抜群に省亭がいい。でも、ああいうのは剥がして持ってくるってことができないじゃないですか。
加島
展覧会がやりづらいですね。
野地
そう。やりづらい。一番大きなふすま絵があるんですけど、それはポーランドにある。(笑)
加島
難しいですね(笑)
野地
さっきの迎賓館のは七宝焼でつくった壁画なんだけど、省亭は実は七宝焼の新たな開発というのも行っている。濤川惣助っていう七宝職人の工房とコラボレーションしている。それまで七宝焼っていうと有線七宝なんです。錫とか金属製の線で輪郭を取って、そのなかに釉薬を象嵌(ぞうがん)していくやり方。省亭と濤川惣助がはじめたのは無線七宝というやり方で、輪郭線を全く取っ払ってグラデーションをつけていく、つまり絵そのままの焼成方法なんです。
加島
没骨描法みたいな?
野地
その通りです。その没骨による無線七宝という技術を開発する訳です。で、それですごくまた人気を得て、海外でも高く評価されます。ハリリさんという日本の工芸を集めている人がいるんですけど、そのハリリコレクションに入っている。で、ロンドンにあるんです。
加島
また海外だ。
野地
そうなんです。だから、いずれ省亭の展覧会はやりたいなと思うんだけど、よほど予算と覚悟を決めないとできない。(笑)でもいずれできると思ってます。ヨーロッパやアメリカからどうやって持ってくるかという手だてがあればできると思いますし、僕の目の黒いうちにやりたいなと。
加島
ぜひぜひ、やっていただきたいです。こういった人たちがまた再評価されるとわれわれ商売人もまたありがたい。(笑)
野地
また、省亭の箱書きっていうのは、共箱がすごく多くて、これはつまり、お弟子さんがいないということなんですね。
加島
なるほど。
野地
省亭は弟子を一人も取らなかったというふうにいわれています。でも最近分かったんだけど、外国人のお弟子さんがいるんですよ。たとえば、トネットっていうドイツ人の理学教師がいますけど、あの人は省亭のお弟子さんなんですよ。
加島
へぇ!そうなんですか。
野地
ええ。その他にも何人か外国人のお弟子さんはとっていたようです。ただそれも本格的にではなく、趣味程度のもので終わっちゃっていますね。お弟子さんがいなかったということで、よけい名前や作品が今に伝わっていないということはいえますね。
加島
では、省亭の師匠、菊池容斎についてもうかがえますか。
野地
省亭は幕末の16歳くらいの頃に容斎のお弟子さんに入ってるので、晩年10年くらいしか容斎に習ってないと思うんです。その当時、80代の容斎は本当におじいさんですよね。親子どころか、祖父と孫のような感じですよね。
加島
ちょっと見てください。これ容斎の作品なんですが。
野地
これすごいね。誰を描いたんだろう。箱書きある?
加島
箱の画題は「本多平八郎沈勇図」と書いてますね。画題は小牧長久手の合戦ってことですよね。78歳って描いてあります。
野地
78歳だと慶応元年頃。本当に幕末ですよね。
加島
容斎の箱書きは弟子の松本楓湖が書いていることが多いですよね。
野地
多いですね。つまり共箱の習慣がまだないからね。それから容斎っていう人の作品は絵解きのための図絵なんです、制作の理由が画面にあるんですよ。
加島
あぁなるほど!そういうことなんですね。
野地
やっぱり容斎っていうのは学者なんで。なんでも調べ上げて、他人にこの人がどういう人なのか、どういう人生を送った人なのかっていうのをお話しするための絵解き図なんですよ。
加島
あ、そうなんですか。
野地
たとえばこの本田平八郎は、小牧の合戦で武勲を立てた人なんだっていうことを講話するための絵解き図なんです。
加島
なるほど、だから箱書きの必要がなかったわけだ。
野地
容斎は、今でいう公民館みたいなところに人を集めて、絵解き図を見せて話をするわけなんです。
加島
別にそれが職業ではないんでしょ?
野地
職業ではない。たぶん求められるままに。容斎先生はそういうのが得意だからっていう風にね。特に天皇に尽くした人を取り上げるというのはすごく多いですね。『前賢故実(ぜんけんこじつ)』という版本を何年かにわたって作り上げていくんだけど、天皇に仕えた古代から南北朝時代までの人たち571人を調べ上げたものです。それも20年くらいかけて作るわけ。それを明治元年、80歳のときに20巻にして上梓するんです。本人はそこまで尊王派でもなかったと思うんですよね。でも逆に尊王攘夷派に利用されたっていうことはありそうですよね。
加島
なるほど。
野地
ちなみにね、容斎の教育方法ってなかなかおもしろいんですよ。たとえばモデルを部屋の真ん中において、その周りを回りながらデッサンをするんです。つまり立体的な把握の仕方を当時からさせていた。それから、今でいう美術解剖学みたいなことを蘭法医の先生を呼んで講釈させたり。あとは容斎がお弟子さんを連れて町を歩いたり。でも野外でスケッチするより、ぶらぶら歩いていて目で覚える訓練をするんですよ。たとえば、あの町のあの街角で会ったあの女の人の髪型を描いてご覧、とかね。気が抜けないわけですよ。常に集中して緊張感を持っていろんなものを見なきゃいけないし、目で覚える訓練をする。省亭はそれを書き残している。記憶力・デッサン力が自然と身についた、と。
加島
確かに記憶力は、そりゃあつくでしょうねぇ。
野地
かなり概念的なことを当時からしている。それと、ひとつの画風にとどまることをすごく嫌ったんですね。だから狩野派が基本だけども、円山四条派もやり大和絵もやり琳派もやりっていうことを率先してやった人。だから、近代美術教育を先取りしている。
加島
なるほど、教育者ですね。
野地
なんで容斎の研究をするかっていうとね、速水御舟とか今村紫紅の先生が松本楓湖でしょ。で、その先生が容斎じゃないですか。楓湖の画塾に入るとまず前賢故実の模写から入るんですよね。近代の美術のなかで紫紅とか御舟の出自って大和絵派といわれているんですけど、でもあれ、容斎派なんですよね。容斎だから、いろんな画風が入り込んでて当たり前なんですよね。で、楓湖も弟子たちに容斎と同じような教え方をやっているから、そのもとを辿ると容斎なんだよね。そういう関心から容斎までいったんですよ。で、容斎の末裔の人って、東京に何人もいるんです。で、ほとんどが医者と科学者。
加島
ほぉ。やっぱり勉強家なんですね。
野地
そういう知識欲がすごくある人達なんだよね。そのうちのひとりの家には、明治4年、84歳のときに描いた容斎の自画像があるんですよ。当時、自画像を描く習慣は日本にはあまりないですよね。つまり西洋の考え方が入っていないと、自画像は描かないんですよね。つまり、新しいもの好きなんですよね、この人は。ものすごく。
加島
世界に目を向けるっていう姿勢は、弟子の省亭に受け継がれていますね。今回は、渡辺省亭と菊池容斎を中心に、明治時代の美術についてお話を伺いましたが、いかがでしたか。
野地
明治時代、特に30年代以降は日本の美術マーケットが整備され始める時期でもあるんです。美術館はまだありませんから、余裕のある好事家たちが、好きな画家を贔屓にするっていうことを始めるんですよ。たとえば原三渓だったら琳派を買い集めてね、それを大観や観山や靫彦や紫紅に見せてね、で彼らはそこで本物の琳派を初めて知るわけです。そうやって近代の琳派、新琳派が生まれてくる。マーケットが広がるだけでなく、マーケットから新たな絵が生まれてくる。
加島
いい流れですよね。そう考えると先生。今は全く逆のような気がしませんか?
野地
そうですね、逆ですね。ある意味ではグローバリゼーションというか、欧米の新興金持ちの人たちが現代アートを買うのは、大正期と同じ流れとも言われるんだけど、でも根本的に美術マーケットが変わらないといけないですね。 |
Profile
加島盛夫
株式会社加島美術
昭和63年美術品商株式会社加島美術を設立創業。加島美術古書部を併設し、通信販売事業として自社販売目録「をちほ」を発刊。「近代文士の筆跡展」・「幕末の三舟展」などデパート展示会なども多数企画。
野地耕一郎
1958年、神奈川県生。成城学園で美学美術史を専攻。1983~97年の間、山種美術館学芸員として勤務。その後、練馬区立美術館主任学芸員として勤務した後、現在は、泉屋博古館にて学芸員を務める。
※上記は美術品販売カタログ美祭12(2012年10月)に掲載された対談です。