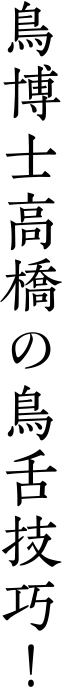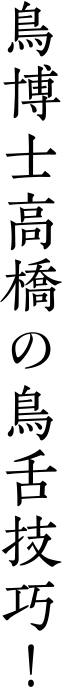vol.04 夏くいなと冬くいな:水鶏
水辺の風景である。手前の葦(ヨシまたはアシ:主に水辺に生え、背丈が3m を超える高茎草本)は暗緑で濃く、奥の葦は薄墨でかなり淡く描かれており、奥行きを感じさせる。葦は疎らで背丈はそれほど高くない(1.5m 程度だろうか)一方で、下草は全く無く、ここが当に水際であることが分かる。葦の葉は向かって右側へ傾いており、そちらに空間(すなわち水面)なのだろう。左手から1 羽の水鳥が歩き出てきた。この鳥はクイナという。
クイナ類(ツル目クイナ科の一部)は湿地・水田・森林などに棲む中型の鳥で、日本にはおおよそ12 種類が生息する(有名な種としては、沖縄本島北部の山原(やんばる)地域だけに生息する森林棲のヤンバルクイナがある)。飛ぶよりも歩く方が得意で、ひょこひょこと歩き回っては足元の小動物を摂食する。その動作や様子は、確かにニワトリ(鶏)に似ている。
その中で最も一般的な種はヒクイナ(緋水鶏;体長23cm)とクイナ(水鶏;体長29cm)で、どちらも河川・湖沼・水田などの水辺の草地に生息する。前者は日本全国で繁殖するが西日本に多く、北海道や東北地方では少数が夏にだけ渡来する。名前の通りに全身が暗い緋色で、特に脚は鮮やかで美しい。初夏に「キョキョキョキョ・・・」とよく鳴いて目立つため「夏くいな」と呼ばれ、古来より文学作品や芸術作品で多く取り上げられてきた。一方で後者は北海道や東北地方で主に繁殖し、東北地方南部以南で越冬する。関東地方から近畿地方にかけては冬鳥であったので「冬くいな」と呼ばれていた。こちらは、文学や芸術に取り上げられたことはほとんど無かった。
本作品では大変珍しいことに、クイナが描かれている(省亭は『赤坂離宮花鳥図画帖』(東京国立博物館蔵)でもクイナを描いている)。嘴は長く基部は薄い橙色で塗られ、目は薄い赤みがある。顔は淡い青灰色、体は茶色で背には細長く黒い縦斑がいくつかあり、腹部には黒地に白や薄茶の横斑が入っている。足は暗い橙色で、足先は水の中にある。その描写はかなり正確で、さすがは省亭である。また、薄い橙色の嘴、薄い赤色の目、青灰色の淡さと少なさ、腹部の薄茶の横斑から、このクイナは冬羽の成鳥または若鳥だと分かる。ちなみに夏羽の成鳥は、青灰色が顔から胸にかけて濃く広がり、嘴は赤く鮮やかになる。
ここで矛盾に気づく。冬羽のクイナが夏の風景の中に居る、このミスマッチをどうして省亭は描いたのだろうか。そもそも省亭はなぜ「冬くいな」を選び、一般的な画題であろう「夏くいな」を避けたのだろうか。十二幅対の六月の絵なのだから、「夏くいな」のヒクイナこそが画題に相応しかったのではなかろうか。私は、この作品の制作時期と初出へのこだわりが、省亭に冬羽のクイナを描かせたのではないかと考えた。
本作品の制作時期、少なくともクイナが描かれた時期は、おそらく冬だったのだろう。ここまで正確に描写しているのであるから、省亭はクイナの実物を観察し、目前で写生して描いたに違いない。省亭が暮らしていた関東では、クイナは冬だけに見られる冬鳥である。よって省亭は、クイナを冬に見て描く他無かったはずであり、それは冬羽のクイナだったはずだ。ひょっとしたら、夏羽のクイナは体色が変わって鮮やかになることを、省亭は知らなかったのかもしれない。
加えて、これまでの日本絵画にクイナがほとんど描かれていなかったことを、省亭は意識していた可能性がある。彼は「その鳥が初めて描かれた絵画」を求めて、意図的にヒクイナを外してクイナを選んだのではないだろうか。芸術の世界でも科学の世界でも、初めての試みは大きな価値がある。省亭にとって本作品は、「日本絵画初出の鳥」を描いた、絵師としても鳥好きとしても誇らしい絵であったのだろう。
高橋 雅雄
(鳥類学者 理学博士)