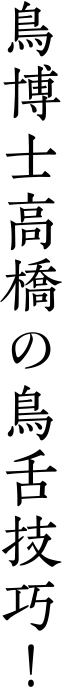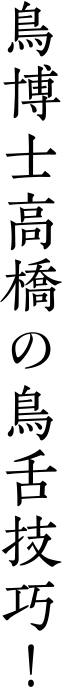vol.16 世界で身近な鳥の存在意義:春野鳩之図
省亭は日本在来の野鳥を主な画題としていたが、勿論いくつかの例外が見られる。その1つであるドバトは、元々は南ヨーロッパ・北アフリカ・中近東・南アジアに生息するカワラバトを家禽化したもので、食用・愛玩用・伝書用・レース用等のため世界各地で飼育されている。日本には平安時代までには伝来したようで、古来より神社仏閣で少数が放し飼いされていたようだ。さらに明治時代には改良が進んだ伝書鳩が欧米から多く輸入され、軍事通信のための軍用鳩として利用された。戦後は鳩レースが人気になり、ドバトの飼育が一般市民にも広まった。現在では、それら飼育個体が再野生化したドバトが野外で繁殖するようになり、都市部を中心に数多くが見られるようになっている。
省亭はいくつかの作品でドバトを描いており、出世作の1つである「群鳩浴水盤ノ図」(フリーア美術館蔵)をはじめ、「銀杏群鳩之図」(齋田記念館蔵)や「もみじに群鳩の図」(個人蔵)などの秀品がいくつかある。中でも本作品は、春の野に3羽のドバトが遊び、省亭作品の中で随一に明るく可愛らしい。ドバトの頭上には枝垂桜が咲き、周りにはタンポポ、レンゲ、スミレ等の草花が小花を咲かせ、ツクシ(スギナ)やワラビが生える。配色は優しく、陰影は無く、画面の隅々まで明るい春の盛りが表現されている。

渡邊省亭「銀杏群鳩之図」
(一般財団法人 齋田茶文化振興財団・齋田記念館)
さて、日本在来ではないドバトは、省亭にとってどのような意味を持った画題だったのだろうか。彼はドバトをどのような存在として扱っていたのだろうか。彼のドバトの作品を俯瞰して考えてみたい。
第1に、ドバトは彼が欧米を強く意識したために採用された画題だったのではないだろうか。ひょっとしたら、最初期に描かれた「群鳩浴水盤ノ図」は、身近な寺院で日常的に見ていた風景を、何の意図も無くありのままに描いたものだったかもしれない。しかしそれは、彼に日本画家初の洋行を実現させたきっかけとなり、フランスの地でエドゥアール・マネの弟子画家に買い取られて、最終的にはアメリカの美術館に収められた。この成功体験によって、彼は自分の芸術性や描写技術が世界に通じる自信を持っただろうし、それと同時にドバトという画題もまた世界に通じることを実感したに違いない。初めて眺めるヨーロッパの景色には見慣れぬ鳥が多かったはずだが、ドバトはヨーロッパの地でも同じ身近な鳥であることに彼は気がついた。彼が生み出す芸術性の多くの部分を超絶技巧の写実性が占めるからこそ、欧米での正当な評価を望むならば、世界中どこでも身近な鳥であるドバトこそが、その写実性が最も理解される画題であると考えたはずだ。後に制作されたいくつかのドバト作品は、桜・銀杏・楓等の彩り豊かな樹木と共に描かれている。これら日本の樹木は庭園芸術の流れから欧米で既によく知られており、これらとドバトを組み合わせた作品群は、欧米での評価を目指して確信的に制作されたものだったかもしれない。
第2に、ドバトは多様な羽色を持つため、色の調和を図るのに都合がいい画題だった可能性がある。都市公園や駅前等で群れているドバトをじっくり観察すると、1羽1羽で羽色がかなり異なり、同じ色模様のものはほとんどいないことに気づく。一度家禽化されたため、体の一部または大部分に白い羽毛があるドバトが多く、その色模様は個体間で大きく異なる。また、灰色や黒い個体はキラキラと輝く羽毛が頸部にあり、その光沢は個体間で異なる(これを構造色といい、省亭は本作品で光り具合を的確に表現している)。他にも体羽や翼の羽にさまざまな色模様があり、これらが総じて羽色の大きな多様性を生んでいる。そのため、ある程度の規則に従ってさえすれば、どんな色模様のドバトも現実的に在り得る存在になり(赤・黄・緑・青などの原色は無いが)、画面の雰囲気や背景の色合いに合わせてドバトの配色を自由に変えることができ、それでも彼の写実性は損なわれることが無い。写実性を重んじた省亭にとって、羽色をある程度自由に変えても不自然じゃないドバトは、大変ありがたい画題だったに違いない。
Click here for English.
高橋 雅雄(鳥類学者 理学博士)
1982年青森県八戸市生まれ。立教大学理学研究科修了。
専門は農地や湿性草原に生息する鳥類の行動生態学と保全生態学。
鳥と美術の関係性に注目し、美術館や画廊でのトークイベントに出演している。
今回のコラムでご紹介した《銀杏群鳩之図》を所蔵する美術館
一般財団法人 齋田茶文化振興財団・齋田記念館
〒155-0033 東京都世田谷区代田 3-23-35
Tel:03-3414-1006
WEB : http://saita-museum.jp/