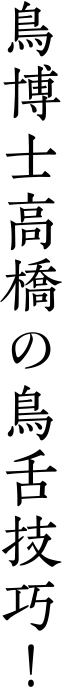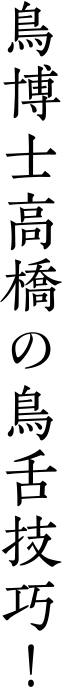vol.20 瑠璃より橙:柳に白菊の雙幅
一見簡素な作品である。柳の幹は簡略的な一筆書きである一方で、手前の細枝や葉は繊細に描き込まれている。そこに橙色の目立つ小鳥がとまる。彼は顔を少し上げ、左目の視線だけをこちらに向ける。彼と鑑賞者が互いの存在に同時に気づき視線が交差する、まさにその一瞬が画面に封じられている。彼に奪われた私の視線はなかなか離し難い、それほど魅惑に満ちた作品である。
この小鳥はジョウビタキ(体長14cm)といい、東アジアの温帯域に分布する。日本では主に冬鳥として全国に渡来し(最近では長野県などで少数が繁殖している)、北日本や降雪地域ではかなり少ないが、その他の地域では比較的多く見られる。里地や里山で暮らし、都会の公園や社寺林、個人宅の庭先でも出会うことができる、かなり身近な鳥である。彼らの一番の魅力は、なんと言ってもその見た目であろう。大きな頭と目、小さな体と嘴、少し長めの尾と、一般的なイメージ通りの小鳥らしいカワイイ姿形をしている。羽色は雌雄で大きく異なり、雌は全身が薄茶色で、腰と尾の一部だけが明るい橙色に染まる。カワイイ顔にシックな装いの“オシャレなお嬢さん”である。対して雄はかなり派手だ。銀色の頭に、黒い顔と翼、橙色の腹と腰と尾を持ち、翼には大きな白斑が目立つ。銀髪に黒い上着と橙色のスーツパンツでキメた“着飾ったジャニーズ系アイドル”とでも言えようか。この雄の外見は画家の制作意欲を刺激し続けたようで、いくつかの絵画作品に登場している。中でも長谷川等伯の「恵比須大黒・花鳥図」(京都国立博物館蔵)や菱田春草の「落葉」(永青文庫蔵)は、時代を代表する秀作である。省亭も気に入っていたようで、本作品だけでなく「桜にひたきの図」(齋田記念館蔵)にも雄のジョウビタキを写実的に描いている。
さて、このジョウビタキはコマドリ・コルリ・ルリビタキ・ノビタキなどと一緒に小型ツグミ類と呼ばれ、かつてはクロツグミやトラツグミなどの大型ツグミ類と共にツグミ科を形成していた。現在はオオルリやキビタキなどのヒタキ類なども加わってヒタキ科に再編されている。このヒタキ科は、ジョウビタキと同様に、雄は華やかな色合いのものが多い。コマドリやムギマキは明るい橙色、トラツグミやキビタキは鮮やかな黄色、オオルリ・コルリ・ルリビタキ・イソヒヨドリは輝く瑠璃色を持ち、どれも愛鳥家に大変人気がある。
このヒタキ科の中で、省亭はどのような種類を選んで描いてきたのだろうか。東京美術が発行した「渡辺省亭-花鳥画の孤高なる輝き-」や齋田記念館が発行した「花鳥礼讃-渡邊省亭・水巴-」、他の画集やインターネットなどから省亭の作品を概観し、描かれたヒタキ科をピックアップしてみよう。該当した作品はあまり多くなかったが、小型ツグミ類としてジョウビタキ・コマドリ・アカヒゲが、大型ツグミ類としてツグミ・シロハラ・クロツグミが数点ずつ見出せた。これら描かれた種類に共通するのは、その主な構成要素が白・黒・橙の3色であることだ。一方で他の色の鳥、特にオオルリやルリビタキなど青い種類は、画題として最も魅力的であろうに、私の知る限り全く描いていない。この色の偏りは何を意味するだろうか。
省亭は白・黒・橙を好んでいたわけではなく、青を避けていたのではないかと、私は推察している。青は赤と共に強い色である。少量でも画面の印象を大きく変え、鑑賞者の視線を集めてしまう。その美的魅力は抗しがたいが、その破壊力は御しがたい。彼独特の静寂の画面には、目立つ青はあまりにも強過ぎたのだろう。ただし、彼は青をけっして使わなかったわけではない。他色を際立たせるための補助色として所々に青を使ったような形跡があるし、アジサイやアサガオなどの花には、青がしっかりと使われている。けれども鳥を描くにあたっては、オシドリを取り上げた第13回でも述べたが、省亭は青の目立つ使用を避ける傾向があったと思う。そのため、青い小鳥は意図的に描かれなかったのではないだろうか。
以上はあくまでも私の勝手な推察である。もしかしたら、青い小鳥が描かれた省亭の絵画作品が現実に存在するかもしれないし、美術界には広く知られているものなのかもしれない。この私の推察は前提がそもそも間違っていて、既に破綻しているのかもしれない。けれども私はそれで構わない。省亭が描いた青い小鳥は、間違いなく魅力的なはずだ。それをこの目で見たいという願望の方が、今の私には勝っている。
高橋 雅雄(鳥類学者 理学博士)
1982年青森県八戸市生まれ。立教大学理学研究科修了。
専門は農地や湿性草原に生息する鳥類の行動生態学と保全生態学。
鳥と美術の関係性に注目し、美術館や画廊でのトークイベントに出演している。